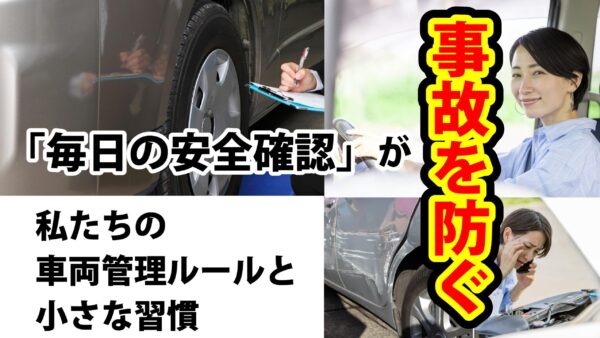皆さん、こんにちは。まるっとけあグループの平田です。
今回は「誤嚥(ごえん)」について、現場での体験を交えながらお話しします。
誤嚥ってなに?
誤嚥とは、本来食道に入るべき食べ物や飲み物、唾液などが誤って気管に入ってしまうことです。
つまり、飲み込みがうまくできずに「変なところに入ってしまう」状態。これが肺に到達してしまうと、誤嚥性肺炎という深刻な健康リスクになります。
誤嚥の仕組みとリスク
食事をするとき、私たちは口に入れた物をゴクンと飲み込みます。
本来であればこれは食道に入り、胃へと運ばれます。
しかし何らかの理由でこれが気管に入ってしまうと、「誤嚥」が起きます。
高齢者の場合、この誤嚥が原因で肺に炎症を起こし、肺炎に至ることが多いのです。
実は、健康な私たちでも夜間に少量の唾液を誤嚥しているとされています。
ただ、健康な人は免疫力があるので肺炎にはなりません。一方で、高齢になると免疫が低下し、同じ誤嚥でも重篤な状態になりやすいのです。
誤嚥のタイミングは「食事中」だけじゃない!
誤嚥は食事中だけに起こるものと思われがちですが、実は寝ているときや何気ない瞬間にも起こり得ます。
むせ込みや咳が増えてきたら要注意。それが、誤嚥のサインかもしれません。
ケアマネ視点での「誤嚥対応」
ケアマネージャーとして、誤嚥のリスクを把握するのは非常に難しい課題です。
現場では、看護師やヘルパーさんと連携しながら、「むせる頻度」や「食事中の様子」などの情報を収集しています。
誤嚥の検査方法
誤嚥が疑われる場合、以下のような検査を行うことがあります:
造影検査(VF):飲み込み時の様子をX線で確認
内視鏡検査(VE):カメラを使って喉の中を直接観察
最近では、耳鼻咽喉科で内視鏡検査を行えるケースも増えており、ケアマネとしても病院や専門医と相談しやすくなっています。
誤嚥対策のための連携とは?
- 食形態の見直し(ペースト食、きざみ食 など)
- 食事介助の支援強化
- 言語聴覚士(ST)によるリハビリ提案
これらはすべて、チームケアの連携があってこそ実現できることです。
誤嚥は「命に関わる」ことがある一方で、早めの気づきと対策でリスクを大きく減らすことができます。
ケアマネージャーとして、そしてチームの一員として、日々の観察と小さな変化のキャッチが重要だと感じています。
以上、現場からの誤嚥エピソードでした。
この記事が、皆さんのケア現場やご家族の支援に役立てば嬉しいです!