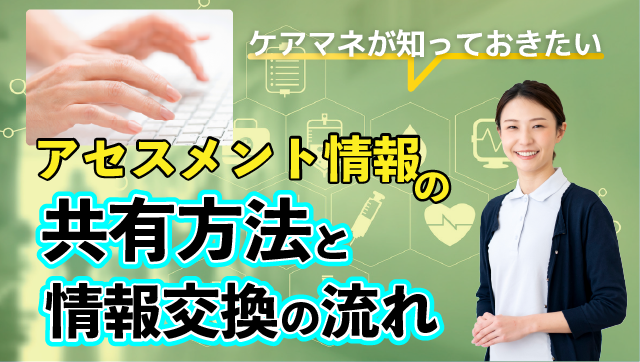ケアマネジャーが日々行っているアセスメント。
これは単なる書類づくりではなく、利用者一人ひとりの人生と向き合い、その人らしい生活を支えるための出発点です。
ただ、現場では「時間が足りない」「病院との情報連携がうまくいかない」「本人が本音を話してくれない」など、さまざまな壁にぶつかります。
この記事では、そんな実情も交えながら、アセスメント情報の共有と医療・福祉職との情報交換について紹介します。
アセスメントとは何か
アセスメントは、利用者の心身の状態や生活環境、介護力、本人の希望などを多角的に把握し、支援の方向性を考えるプロセスです。

「一番大変なのは病院との連携。連絡しても情報を出してくれない。結局、本人の話と家族の話から何とか組み立てることが多いです」

「初対面の場面で、どこまで踏み込んで聞いていいのか、毎回迷います。本人が答えたくないこともあるし、家族がその場にいると本音が出ないこともある」
特に病院から在宅に戻るタイミングでは、病院側から情報が出てこないと利用者の人物像がつかめず、支援の方向性もブレやすくなります。「医療連携って本当に成り立ってるの?」と感じることも少なくありません。
自宅や施設に訪問しても、単に情報を聞くだけでは信頼関係は築けません。
生活歴や価値観、その人が大切にしてきたことを探りながら、少しずつ本音を引き出す。
時間も手間もかかる仕事です。
医療職・福祉職との情報交換の流れ
アセスメントの情報は、医療職や福祉職と共有することでより深みのある支援につながります。
しかし、現場には理想と現実のギャップもあります。
1. 事前情報の収集
アセスメント前に、主治医や看護師、リハスタッフ、訪問ヘルパーなどから情報を集めます。
バイタルやADL、最近の体調変化などが中心です。

「主治医から有益な情報が出てくることって正直あまりない。現場のリハ職や看護師さんからの声の方がよほどリアルで役立つ」

「連絡しても、事務的な返答だけで『詳しくは記録を見てください』という病院も。そんな簡単に記録もらえないし…って毎回思います」
2. アセスメントの実施
本人や家族に聞き取りを行い、生活状況や身体状況、認知機能、社会とのつながりなどを確認します。

「最初の訪問は緊張感がすごい。本人が警戒していたり、家族に不信感があったりすると、なかなか本音が聞き出せません」

「一見問題なさそうに見えても、よくよく聞くと“家の中で毎日怒鳴り声がしている”とか、“ご飯をほとんど食べていない”とか、深刻な話が出てくることもある」
3. 情報の整理と分析
集めた情報は、家族や本人に再確認しながら丁寧に整理していきます。

「あとで『そんなこと言ってない』とならないように、必ず確認しながら進めています。特に家族間で意見が食い違うときは慎重になります」

「認知症の方だと、言っていることが日によって違ったり、現実と違うことも混じる。そういうときは、現場職員の観察や、複数回の訪問で少しずつ確かめます」
4. 情報共有会議(サービス担当者会議)
ケアプラン原案をもとに、関係事業所が集まって意見交換する場です。

「長期や新規の際、サービス担当者が全員訪問すると、ご家族に『こんなに大勢で来るなんて迷惑』と言われることもあります。本当は負担をかけたくないのに…」

「せっかく集まっても、『あとはケアマネさんにお任せします』で終わる職種もいて、丸投げ感がすごい。もっと一緒に考えてほしいと思うことがよくあります」
5. モニタリングと再アセスメント
サービス開始後も、月1回程度訪問し、状態の変化や支援内容の見直しを行います。

「訪問すると、ご家族が介護に疲れていたり、兄弟間で揉めていたり、予想外の課題が見えてきます」

「長女が母親を怒鳴っていたり、夜間徘徊が始まっていたり、サービス開始後もアセスメントし直しになることは多いです」

「全ての利用者に月1回の訪問が必要か?と問われると、正直分からない(疑問)。訪問したことで関係がこじれることもあります。本音としてはケースバイケースで柔軟にしたいところ」
情報交換で大切なこと
連携がうまくいっている現場では、次のような点が意識されています。
- 共通の言葉で話す
「この人は介助が必要です」と言っても、職種ごとにとらえ方が違うことがあります。共通フレームで整理すると理解しやすくなります。 - データと現場感覚のバランス
血圧や歩行状態などの数値と、実際の暮らしの中での様子を組み合わせて伝えることで、よりリアルに伝わります。 - 役割分担の明確化
「これは誰が担当?」「こっちはいつからスタートする?」を明確にしておかないと、後でトラブルになります。 - 最新情報の共有
状況は常に変わるため、連絡がこまめに取れる関係性づくりも重要です。

「お互いが“情報を出し惜しみしない”って気持ちがないと、うまくいかない。現場でギスギスするのは、大体そこに原因があります」
アセスメント様式の違いと工夫
アセスメント様式は事業所によってバラバラですが、大切なのは「伝わる情報になっているか」です。
- 居宅介護支援事業所:「居宅サービス計画ガイドライン方式」(37.7%)
- 介護老人保健施設:「包括的自立支援プログラム方式」(29.8%)
- 独自様式を使用している事業所も多数

「結局、使いやすいように自分たちで様式を作っちゃう。形式よりも“必要な情報が入っていて、誰にでも理解できる”が一番大事です」
おわりに
アセスメントは、利用者の生活の核心に触れる仕事です。そして、それはケアマネ一人でできるものではありません。多職種と協力し、相手の立場に立って情報を交換していくことが、よりよい支援につながります。
現場の課題は尽きませんが、「この人にとって一番良い支援は何か」を考え続けることが、ケアマネとしての仕事の核であることに変わりはありません。
「事前説明会」随時開催!

入社を悩んでいる方、今すぐではないけど入社を検討されている方等、お仕事関する疑問や不安を取り除いていただくために事前説明会を随時開催しております。
お申込みの際は、「ご希望日時」を必ず入力ください。(日程調整の上、ご返信させていただきます。)
また、事前に質問内容や確認事項などをご入力いただけますと、資料などをご用意いたします。
当日の面接(履歴書、職務経歴書、免許証(資格証明)、筆記用具持参)も可能です。
勤務日、勤務時間等のご希望を考慮致します。まずはお気軽にご相談ください。